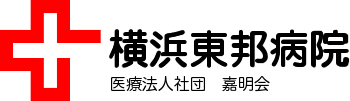災害時の備えは…?
勉強会・連絡会議など
皆様こんにちは。
横浜東邦病院 事務スタッフの坂本です。
8月に入って早々、雷が落ちたりと若干荒れた気候になっていますね。
上大岡近辺でも深夜に停電が発生し、朝からいくつか機器が止まっていたりとトラブルが残っているようでした。
そんな災害報告を聞いた折にふと先日行った勉強会を思い浮かべたので、ご紹介いたします。
その勉強会の内容は・・・ 「非常用トイレ」について、です!
当院では先の東日本大震災を受け、院内で複数個のポータブルトイレを導入しています。

震災などの際、毎回のように問題提起はされますが、報道などではほとんど報じられない「排泄問題」。
21年前に発生した阪神大震災のときは、仮設トイレの設置自体は震災の翌日から始まりましたが
十分な数が行き渡るまで2週間かかった、と言われています。
そして設置後の問題も発生しています。
仮設トイレは家庭などの水洗式とは違い汲み取り式になります。
そのためトイレはあっても、震災の影響でバキュームカーが通ることができない箇所がたくさんあり、
汲み取りが行われずに結局タンクがいっぱいになって使用不可……などといった、処理の問題も多数挙げられました。
汲み取り式がだめなら固液分離・殺菌処理を行い水分を流すことができるポータブルトイレを使えばいいじゃない!と
組み立て式のトイレの配布が行われたところもあります。
が!
今度はまた別の問題が持ち上がります。
こういった災害用に設計されたトイレは非常に便利ですが、
「組み立て方・使用方法がよくわからないまま使われていた」ということもあったそうです。
つまり、メリットである「排泄後の処理が簡単に行える」という最大の利点を活かし切れていなかったということです。
日本トイレ研究会のアンケート調査でも、
3時間以内にトイレに行きたくなった人 31%
4~6時間以内にトイレに行きたくなった人 36%
という結果もあり、食事とは異なり排泄は常に待ったなしな状況。
そういった状況からトイレにいくまい!と、食事・飲水を控えて脱水症状を起こしたりと、健康被害も発生しています。
東日本大震災では教訓を活かし仮設トイレの配備も早めに行われてはいたようですが、それでも一番遅い自治体には
65日後にようやく設置が行き渡ったという調査結果もでています。
前置きが非常~~~に長くなりましたが、まさに死活問題ですね。
当院でも前述の通りポータブルトイレの配備はあり、その際に業者による使用説明会も行なっております。
しかし!こういった非常用ポータブルトイレ、有事以外ではまず使いません。
(当然使うような状況がないにこしたことはありませんが…!)
そのため、「使い方なんて覚えてないよ…」という方や、説明会の後に入職した職員など、
使い方を把握している人が非常に少ない状況に。
そんな背景もあり、今回はおさらいの意味も込めての勉強会開催の運びとなりました。

さきほどの箱に、このようにビニールを設置します。
上はすでに便座になっているため、そこに座って排泄をするわけですが…

用を足す前にこの凝固剤をビニールの中に投下します。
これにより排泄物が固まり、ニオイもカット!
そしてそのまま捨てることができると、スグレモノです。
そして排泄が終わったら手元にあるスイッチを押します。
水洗式トイレの流すボタンみたいなものですね。
(このポータブルトイレは電動式ですが、なんとバッテリーでも動かすことができます)

すると機械が動き始め、固めた排泄物がこのようにビニールでラッピングされて出てきます。
(わかりやすいように勉強会の水は色を付けてみました)
凝固剤によってニオイも少なくなっており、ビニールで密閉もされているので、あとはこのまま捨てればOK!
とっても衛生的です!

非常に便利な反面、機械式のポータブルトイレの難点は少々設置が特殊なことにあると思います。
こういった勉強会も定期的に開催して、災害時の備えを盤石にしていきたいですね。

横浜市港南区最戸1-3-16
TEL:045-741-2511
メール:info@yokohama-toho-group.org
Facebook
https://www.facebook.com/yokotohp
横浜東邦病院 事務スタッフの坂本です。
8月に入って早々、雷が落ちたりと若干荒れた気候になっていますね。
上大岡近辺でも深夜に停電が発生し、朝からいくつか機器が止まっていたりとトラブルが残っているようでした。
そんな災害報告を聞いた折にふと先日行った勉強会を思い浮かべたので、ご紹介いたします。
その勉強会の内容は・・・ 「非常用トイレ」について、です!
当院では先の東日本大震災を受け、院内で複数個のポータブルトイレを導入しています。

震災などの際、毎回のように問題提起はされますが、報道などではほとんど報じられない「排泄問題」。
21年前に発生した阪神大震災のときは、仮設トイレの設置自体は震災の翌日から始まりましたが
十分な数が行き渡るまで2週間かかった、と言われています。
そして設置後の問題も発生しています。
仮設トイレは家庭などの水洗式とは違い汲み取り式になります。
そのためトイレはあっても、震災の影響でバキュームカーが通ることができない箇所がたくさんあり、
汲み取りが行われずに結局タンクがいっぱいになって使用不可……などといった、処理の問題も多数挙げられました。
汲み取り式がだめなら固液分離・殺菌処理を行い水分を流すことができるポータブルトイレを使えばいいじゃない!と
組み立て式のトイレの配布が行われたところもあります。
が!
今度はまた別の問題が持ち上がります。
こういった災害用に設計されたトイレは非常に便利ですが、
「組み立て方・使用方法がよくわからないまま使われていた」ということもあったそうです。
つまり、メリットである「排泄後の処理が簡単に行える」という最大の利点を活かし切れていなかったということです。
日本トイレ研究会のアンケート調査でも、
3時間以内にトイレに行きたくなった人 31%
4~6時間以内にトイレに行きたくなった人 36%
という結果もあり、食事とは異なり排泄は常に待ったなしな状況。
そういった状況からトイレにいくまい!と、食事・飲水を控えて脱水症状を起こしたりと、健康被害も発生しています。
東日本大震災では教訓を活かし仮設トイレの配備も早めに行われてはいたようですが、それでも一番遅い自治体には
65日後にようやく設置が行き渡ったという調査結果もでています。
前置きが非常~~~に長くなりましたが、まさに死活問題ですね。
当院でも前述の通りポータブルトイレの配備はあり、その際に業者による使用説明会も行なっております。
しかし!こういった非常用ポータブルトイレ、有事以外ではまず使いません。
(当然使うような状況がないにこしたことはありませんが…!)
そのため、「使い方なんて覚えてないよ…」という方や、説明会の後に入職した職員など、
使い方を把握している人が非常に少ない状況に。
そんな背景もあり、今回はおさらいの意味も込めての勉強会開催の運びとなりました。

さきほどの箱に、このようにビニールを設置します。
上はすでに便座になっているため、そこに座って排泄をするわけですが…

用を足す前にこの凝固剤をビニールの中に投下します。
これにより排泄物が固まり、ニオイもカット!
そしてそのまま捨てることができると、スグレモノです。
そして排泄が終わったら手元にあるスイッチを押します。
水洗式トイレの流すボタンみたいなものですね。
(このポータブルトイレは電動式ですが、なんとバッテリーでも動かすことができます)

すると機械が動き始め、固めた排泄物がこのようにビニールでラッピングされて出てきます。
(わかりやすいように勉強会の水は色を付けてみました)
凝固剤によってニオイも少なくなっており、ビニールで密閉もされているので、あとはこのまま捨てればOK!
とっても衛生的です!

非常に便利な反面、機械式のポータブルトイレの難点は少々設置が特殊なことにあると思います。
こういった勉強会も定期的に開催して、災害時の備えを盤石にしていきたいですね。

横浜市港南区最戸1-3-16
TEL:045-741-2511
メール:info@yokohama-toho-group.org
https://www.facebook.com/yokotohp